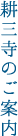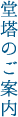館蔵品展 耕三寺と俳句
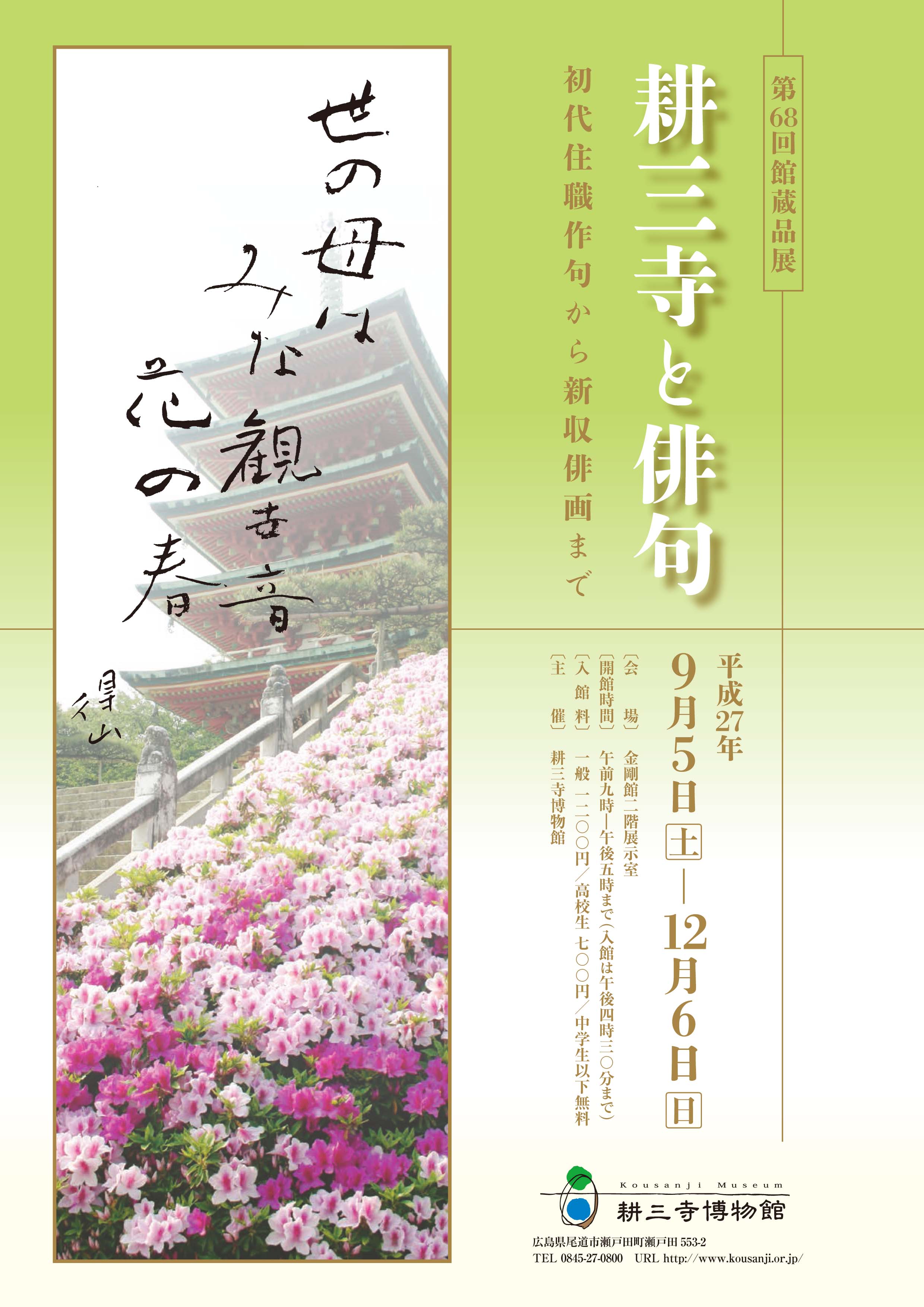
館蔵品展 耕三寺と俳句(金剛館2階展示室) 展示目録
| 作者 | 俳句 | 形状など | 備考 | 新収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初代住職 耕三寺耕三と 師松野自得 |
耕三寺得山 | 世の母はみな観世音花の春 | 軸装 | 俳画(川上拙以筆) | |
| 鐘が鳴る撞けよ浄土の春が来る | 軸装 | ||||
| 仏恩の尊さにふれ塔の春 | 軸装 | ||||
| 島に来れば我も島人春ぬくし | 軸装 | ||||
| 光明にふれんと捧ぐ菊の白 | 短冊 | ||||
| 観世音うららにおはす得山と | 短冊 | ||||
| 町の衆がつく除夜の鐘春がくる | 短冊 | ||||
| よき母と選はれ給ふバラ香ふ | 短冊 | ||||
| 最善寺大王松は繁り澄む | 短冊 | ||||
| 安心をもとめ倖せ菊薫る | 短冊 | ||||
| 花の山国宝塔と師の古句と | 短冊 | ||||
| 白菊の白光捧げ句牌の前 | 短冊 | ||||
| ばら匂ふ孝養門の御佛に | 短冊 | ||||
| 梅薫る島守り給へ彌陀如来 | 短冊 | ||||
| 初夏の朝新妻の化粧更たなる | 色紙 | ||||
| 松野自得 耕三寺得山 |
千佛洞涼し地獄の火も消ゆる 地獄にも御佛おわす春うらら |
軸装 | 俳画(松野自得筆) | ||
| 松野自得 | 盆の月おどってみたくなりにけり | 軸装 | |||
| 信ずれば寺も建つなり花吹雪 | 軸装 | ||||
| 極楽も地獄も法の花盛り | 軸装 | ||||
| 御光は常夜を照す八重ざくら | 短冊 | ||||
| 屠蘇酌めば鶴の齢を得しここち | 短冊 | ||||
| レモン湯ぞ垢を浮べることなかれ | 短冊 | ||||
| 岩に立てば我も巨人ぞ秋の風 | 短冊 | ||||
| 落鮎に河原の石は日々冷ゆる | 短冊 | ○ | |||
| 冷房に来て消に消えつ町の汗 | 短冊 | ○ | |||
| 八方をにらみて立てる鍾馗かな | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||
| 秋の川一里がほどは橋もなし | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||
| 秋の夜の心静かや正信偈 | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||
| 舟人の下りてせわしやラムネの玉 | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||
| 田植笠梅雨の晴れ日を照りかへし | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||
| 桑つみ女はなしがしたく手傳へり | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||
| 近代 俳人の句 |
高浜虚子 | 初富士や草庵を出て十歩なる | 軸装 | 俳画(斎藤雨意筆) | ○ |
| 草抜けばよるべなき蚊のさしにけり | 短冊(軸装) | ||||
| 正岡子規 | 風呂敷をほどけば柿のころげけり | 軸装 | ○ | ||
| 蛍籠行燈に遠くつるしけり | 短冊(額装) | ||||
| 夏目漱石 | 蓮の葉に麩はとどまりぬ鯉の色 | 短冊(額装) | |||
| 中村不折 | かがまって土橋ぬけるやもどり舟 | 短冊(額装) | ○ | ||
| 大谷句仏 | 涼しさに念仏もうす夏百日 | 短冊(軸装) | |||
| 河東碧梧桐 | 島に住めば柑子沢山な正月日和 | 六曲屏風 | 展示期間 9/5~10/18 |
○ | |
| 雪散る青ぞらの又た此頃の空 | |||||
| 子を歩せて下枝々々のさくら咲く方へ行く | |||||
| 明くて桃の花に菜種さしそふる | |||||
| 鮎をききに一はしり小女の崖下りてゆく | |||||
| 汐のよい船脚をせとの鴎はかもめ連れ | |||||
| 河東碧梧桐 | 蜻蛉釣る竿捨てて行ぬよる波に | 六曲屏風 | 展示期間 10/19~12/6 |
○ | |
| 夜も鳴く蝉の灯明りの地に落るこゑ | |||||
| 今宵泊らん脚いたはりつ紅葉濡れゐつ | |||||
| 一軒家を過ぎ落葉する風のままにゆく | |||||
| 山を出て雪のなき一筋の汽車にて帰る | |||||
| 師走の柿奈良よりとどく笹しいて | |||||
| 種田山頭火 | 水音のたえすして茨の実 | 短冊(額装) | ○ | ||
| 近世 俳人の句 |
松尾芭蕉 | くさりつる其風みこそ納豆汁 | 消息(軸装) | ||
| あらたうと木の下闇も日の光 | 軸装 | ||||
| 涼しさを繒にうつしたり嵯峨の竹 | 軸装 | 俳画 | |||
| 服部嵐雪 | 真夜半や振替りたる天川 | 短冊(軸装) | |||
| 竹のはを遊びあるけよ露の玉 | 短冊(軸装) | ||||
| 宝井其角 | なつかしき枝のさけめやうめの花 | 軸装 | 俳画 | ||
| 廬崎や江戸をはなれぬいかのぼり | 軸装 | 俳画 | |||
| 向井去来 | 目を病し妹に真桑をかくしけり | 軸装 | |||
| 雪と花の中に出るや春の月 | 短冊(軸装) | 俳画 | |||
| 上島鬼貫 | けふ丸き末もいく露菊童子 | 消息(軸装) | |||
| 加賀千代女 | 菊咲や揺やし行もよもあるき | 軸装 | 俳画 | ||
| 大高子葉 | 檜笠いさためさはや神あられ | 軸装 | |||
| 神崎竹平 | 苔清水しのぶにむすぶ古坊主 | 短冊(軸装) | |||
| 近代 小説家の句 |
幸田露伴 | 陽炎や鮒釣る馬鹿の鼻の先 | 短冊 | ||
| 尾崎紅葉 | 新年海 波かけや魚の眼も玉の春 | 短冊 | |||
| 徳田秋声 | 狼の声に豆腐の氷る夜哉 | 短冊 | |||
| 泉鏡花 | 買初に雪の山家の絵本かな | 短冊 | |||
| 永井荷風 | 荷舟にもなびく幟や小鯛河岸 | 短冊 | ○ | ||
| 内田百閒 | 春寒し朝開帳の善光寺 | 短冊 | ○ | ||
| 芥川龍之介 | 藤の花軒端の苔の老いにけり | 短冊 | ○ | ||
| 川端康成 | 初空に鶴手羽舞ふ幻乃 | 短冊 | ○ |
附)松野自得と耕三寺 松野自得句碑紹介パネル
松野自得句集・俳句雑誌『さいかち』


 ENGLISH
ENGLISH francais
francais 中文(繁體字)
中文(繁體字)